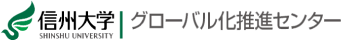現状に縛られず、小さなきっかけを大切に。
近藤 広大さん
理学部 理学科地球学コース
留学期間:2019年 2月 ~ 2019年 6月
留学先:カーティン大学
留学先大学について
僕が留学していたカーティン大学は西オーストラリア州の州都パースにあります。パースと聞いてもイメージがわかない人も多いかと思いますが、一言で言うとオーストラリアの美しい自然と近代的な都市が見事に共生する、オーストラリア西海岸の中心地です。カーティン大学も例にもれず、広々とした公園のようなキャンパスには一面芝生が広がり、澄み渡った大陸の青い空とレンガ調の研究施設とのコントラストはまさにパースの縮図であり、学習・研究の場と憩いの場を兼ね備えた大学です。
そんな、学習しやすいのびやかな環境に加え、カーティン大学には世界100か国以上の国々から留学生たちが集まり、多様な文化・背景をもった学生との交流は、日々、刺激を与えてくれます。
また、図書館にはメーカースペース(3Dプリンターやレーザー・カッターなどを用いてアイデアを形にしていく場)やスリーピング・ポッド(照明・音楽により、起きたい時間に起こしてくれる)が整備されていたり、授業面では毎回の授業が録画されていて、オンライン配信されたりと新しい技術やコンセプトを積極的に取り入れている大学でもあります。
学習面について
・履修について
交換留学生は、1学期につき3, 4科目を履修します。一見すると、さほど忙しくないように思えますが、1科目当たり、週3~4時間授業があるので思ったより忙しいです。日本の一般的な授業とは異なり、いわゆる講義形式のレクチャーに加えて、ラボラトリーやフィールドワーク、ワークショップやチュートリアルなどを組み合わせたカリキュラムになっているため、講義と実習を絡めた内容の濃い授業を受けることができます。また、交換留学生は特定のコースに属さないので、特別な要件が無い限り(語学要件や事前に履修しておくことが望ましい科目の履修 等)、どのコースの科目も履修することが可能です。
・試験や課題
科目にもよりますが、”出席点”がほとんどないため、課題のウェイトが大きい場合が多いです。だいたい1学期に2~3個ほどの課題が課され、1つの課題の成績が成績全体の20~30%を占めることが普通なので、手を抜くと大変なことになります。ただ、課題が重要な分、課題に取り組む際の先生からのサポートも手厚く、オフィスアワーを拡張して質問に答えてくれたり、最終的な提出の前に一度ドラフトを提出すると、フィードバックをもらえたりします。試験についても、多くの場合サンプル問題やヒントが公開されるので、それに従い準備をするといった形でした。
・ついていけるか不安
ほとんど全てのレクチャーが録画されていて、オンラインで視聴することが可能です。万が一聞き逃したことがあっても何度でも聞くことができます。また、教員と学生との距離が非常に近く、気軽に先生の部屋に質問に行くことができます。さらに、僕が履修していた地質学コースでは、例年特に不合格者が多い科目については、上級生がボランティアとして追加授業を行っていたので、肩の力を抜いて安心して授業を受けることができました。
生活について
・寮生活
現地では、大学内の寮に住んでいました。一つのフラットは、ドア付きの個室が6~8個あり、共用のトイレ、シャワー、キッチンに、ソファーやテレビを完備した共有スペースがある、といった間取りでした。個々の部屋には勉強机やベッド、クローゼットやヒーター等が完備されていて、不自由な点はあまりありませんでした。寮では、映画鑑賞やゲーム、季節のイベントやフリーミールなどといった様々な催し物が行われ、他の棟の学生や大学内にある別の寮の学生とも交流を持つことができます。また、フラット内の共有スペースとは別に、大型テレビやビリヤード台、ゲームや楽器類のある寮全体での共有ルームもあり、暇なときはとりあえずそこへ行って誰かと話したり、映画をみたりもできます。
・普段の食事
カーティン大学の寮では食事の提供はおこなっていないので、食事は自炊or外食になります。パースは物価が高く、外食すると一食当たり1,000円を超えてしまうことが普通なので、時間があるときは極力自炊をしていました。オーストラリアは移民が多いため、食文化も多様で、オーストラリアらしい食材(例:カンガルーの肉)に加え、いろんな国から輸入されてきた食品が入手可能です。もちろん日本の食品コーナーもあり、大抵の調味料や有名なお菓子はオーストラリアでも手に入ります。
・大学内
日本と比べるとやはり高くついてしまいますが、学内にはサンドイッチやピザ、フィッシュアンドチップスなどといった定番に加え、メキシコ料理やアジア料理、ハラールの料理等、様々な料理を提供するお店が並びます。また、バラエティー豊かなフードトラックが来るため、食べ物で飽きることはありません。
図書館や主要な建物にはカフェがあり、授業の合間や空きコマに、公園みたいな広場でコーヒーを飲んでリフレッシュすることもできます。
留学で得たこと
英語を用いて生活し、オーストラリアの大学で専攻する分野の学部の授業を履修することで、専門分野である地質学の知識や英語力を向上させることができました。そうした新たな知識の習得はさることながら、これまで出会ったことがなかったような個性豊かな友人、そうした友人との関わりや先生方のご指導、異国の地での生活を通して得た新たな物の見方や考え方こそ、今回の留学で僕が得た最大の収穫であったように感じます。
具体的に言うと、
・社会人経験のある学生や国費で留学する学生たちからは、ほどほどに頑張って授業や課題を乗り越えればいいと考えていた僕に、妥協せずやりきることの大切さと意味。
・英語がほかの教授陣に比べ完璧とは言えないフランス人の教授からは、英語でのコミュニケーションで一番大事なことが、語学力ではなく伝えようとする事柄の芯やその人の人との接し方にあるということ。
・4か月間柔道を通し交流したカーティン大学柔道部の部員たちからは、異なる文化を迎え入れ共に成長していこうとする姿勢。
というように数えたらきりがない多くの貴重な経験・学びができたと感じます。
後輩へのアドバイス、信州大学へのメッセージ等
・後輩へ
学部1年生の時、僕は別の大学の人文学部に所属していました。そこで入学時に受けたTOEICの成績で足切りをされ、海外大学での語学研修に応募することすらできず、留学なんて夢のまた夢だと思っていました。それでも、海外の大学で勉強したいという漠然とした目標が常にあって、留学経験者の成果報告会を聴きに行ったり、留学のための語学力強化の特別授業を受講してみたりしていました。気づけば英語が好きになり、地質学を学ぶといった明確な目標が見つかり理学部へと編入し、延いては、オーストラリアの大学・野外で授業を受けることができていました。
学部1年の時、僕は留学に必要な語学力も、明確な目的や目標も持っていませんでした。今はぼやけたイメージでも持ち続けていれば、達成できるかもしれない、そう思って手放さないでください。
・信州大学・お世話になった方々へ
留学の計画から帰国まで、グローバル化推進センターの方々には大変お世話になりました。また、交換留学や単位互換に関して相談にのってくださった理学部地球学コースの先生方、留学を応援してくれた友人や家族にも心から感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。